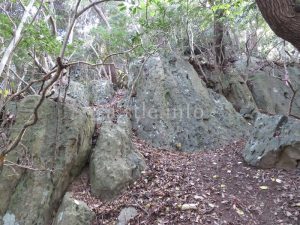2018/11/某日訪問
堀越城、と書くと青森県弘前市のほうを連想されることが多いかもしれないが、訪問したのは北九州市の堀越城である。2014年に北九州市に訪問した際にも寄りたかった山城だが、時間がなかったので寄れなかった。2018年11月に長野城再訪することにしたので、そのついでに堀越城も寄ることにした。
北九州モノレール企救丘駅かJR九州の志井公園駅で下車し、東に進めば登山口にたどり着く。JR九州日田彦山線よりかは北九州モノレールのほうが本数が多いので、公共交通機関で訪問するなら小倉からモノレールがよいかと思う。
この日は先に長野城を訪問したのだが、初回よりじっくり見学したこともあり、予定以上に時間を費やしてしまった。堀越城の上り下りでどれだけ時間がかかるか読めなかったので迷ったのだが、ひとまず登山口と登山道の確認だけはしておこうと山に入った。迷ったのはこの日に関東へ帰る予定だったためである。新幹線の時間が決まっていた。
堀越城のある山には笠岩という岩があり、そこへの登山道は地元の方が整備していることは知っていた。笠岩まで行けばそこから堀越城に行くのは楽なんじゃないかな、と考えていたのだが、訪問前に検索してみたところ、堀越城への道も整備されていることがわかった。時間が気になっていたが、その登山口と登山道をひとまず確認していこうと思ったのだ。
実際は長野城からの訪問になったが、企救丘駅からの訪問方法を記しておく。
道路の南側の歩道を歩いたほうが横断歩道を渡る回数が減るので、企救丘駅は南側の歩道へ下りる。
その後東に進み続けると堀越交差点。こちらも東に進んで岳の観音トンネルが見えてくれば正解。ちなみに岳の観音トンネルの上にある山は丸ヶ口(福相寺)城である。
トンネル西側の山へと続くスロープへは “岳の観音山登山口” の案内がついている。こちら側から丸ヶ口城へ登れるのかもしれないが、この日は試す時間はなかった。
トンネルをくぐって最初の交差点を右に曲がり、東九州自動車道の下をくぐれば登山口につくのだが、その手前に登山口の案内と長野城にまつわる説明版が設置されていた。
縄張り図が載っていたが、それは長野城のもので、堀越城のはなかった。知名度や畝状竪堀を考慮すれば長野城を優遇するのはよくわかる。
なお、麓から見えるのは堀越城の剣立山部分であり、主郭は見えない。
眺望確保のため伐採されているので、どの山かはわかりやすい。
東九州自動車道をくぐると、笠岩の案内標示。途中までは同じルートなのでしたがう。
山道に入ると早い段階で分岐。笠岩には寄らないので剣立山へ。
ちょっと進むと祠がある。ここまでは主に若干のアップダウンのある平行移動が主だったが、これより先は上りとなる。
途中、金の神様の祠があったが、写真のできが悪かったので掲載せず。剣立山への案内はあるので迷うことなく進む。
尾根が見えた。この段階で麓からだいたい20分であった。この調子なら堀越城を見学しても新幹線に間に合いそうだな、と判断したので引き返すことなく続行。
尾根には平場もあるのだが、縄張りではなさそうだ。
進むと若干の岩場。のちに結構な岩場が出てくるのでそれに比べると小規模な岩場。
小規模な岩場を越えると急斜面。
大規模な岩場。この岩場の手前に段曲輪っぽいのもあったが写真ではなんだかわからなかったので掲載せず。この岩場には黄とピンクのリボンがついていて、黄が難で、ピンクの方が楽という感じだった。私は往路は黄、復路はピンクを利用した。
岩場を越えて更に登ると剣立山ピーク。ここは眺望確保のため伐採されているので見晴らしはよい。しかし低木が生え始めているので手入れは必須だろう。
ピークからの眺望。城の物見的役割であろう。堀越城は何度か手が入っているらしく、剣立山部分は古い作りだそうだ。確認しようにも低木が多くて山頂付近は眺望を楽しむ以外に動きが取れず。
剣立山の標。
長野城方面を見る。しかし、どれが長野城だかは現地ではわからなかった。崩壊した林道が見えれば崩れ具合で判別できたのだが。
ここまで剣立山への案内しかなかったので、整備されているのもここまでかな、と思っていたのだが、堀越城への案内標示があったので安堵する。最低限の整備はされているだろう。
剣立山から南側が主郭だが、いったん下ることになる。
下ると堀切。草木の繁茂具合は剣立山より激しいが、歩けないわけではない。
鞍部を進むとまた上りとなり、小さな段曲輪が連なる。
虎口を抜けると主郭だ。城内で一番の広さを誇る曲輪である。
主郭からは三方向に尾根が伸びている。登ってきた剣立山へ続く北東、おそらく笠岩へ続く南東、そして堀越集落へ続いているらしい北西だ。
まずは南東尾根へ。ここの切岸が高くて急。階段があるので助かる。
下ると北側に片堀切があるのだが、写真だとよくわからなかったので掲載せず。
片堀切の先に明瞭な堀切。堀切の先は竪堀になっている。
堀切の先は平場のように見えるが縄張り外っぽい。道は続いているので方角的に笠岩に続いていそうであるが未確認である。
南東尾根から主郭に引き返し、今度は北西へ。
主郭から北西尾根曲輪群へのスロープ。
北西尾根の曲輪群は他の尾根の曲輪より整形がしっかりしており、他の尾根よりは後に造成されたようだ。
2段ほど曲輪をうっすら堀切。
再び登って小城と呼ばれるピークへ。
小城の先を下ると二重堀切なのだが、私の目では幅広の堀切にしか見えなかった。
後半はやはり新幹線の時間が気になってしまい急ぎ足となった。そして初のグリーン車乗車。早割を使ったら指定席の料金と大差なかったのだ。隣には誰もこなくてかなり快適な空間であった。小倉から東京という長距離だったが、指定席で帰るよりよほど楽であった。
隣の長野城ほどインパクトのある城跡ではないが、長野城にはない眺望、低山ハイキングを味わえるので長野城訪問のついでに寄るのもよいかと。こちらは崩落ポイントはなかった。
堀越城位置
堀越城登山口。この座標の南側に明瞭な登山道がついている。